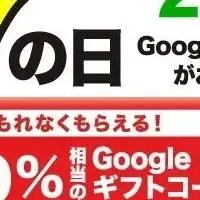

名古屋に新設されたAcompanyの秘密計算研究所・CC Labが描く未来のデータ活用
名古屋に新設されたAcompanyの秘密計算研究所・CC Labが描く未来のデータ活用
株式会社Acompanyは2025年4月1日、名古屋市に新たな研究機関「Confidential Computing Lab(通称、CC Lab)」の設立を発表しました。
この施設は、ハードウェア型秘密計算技術に特化した研究開発を行う専用のラボです。CC Labでは、研究所の設立を通じて、先端技術の開発を進め、学術コミュニティと連携しながら、データとAIの安全な利活用を促進することを目指しています。
CC Labの設立の背景
Acompanyは、2月に、日本国内初となる秘密計算を駆使したセキュリティサービス「AutoPrivacy AI CleanRoom」を発表しました。このサービスは、データとAIのプライバシーを保護するもので、同時にプライバシー規制に対応したデータクリーンルームサービス「AutoPrivacy DataCleanRoom」の提供も行っています。
これらのプロダクトには、Acompanyのコア技術としてハードウェア型秘密計算が組み込まれています。
今後、Acompanyの製品をさらに進化させ、データとAIの安全な活用を促進するためには、ハードウェア型秘密計算を基盤とした技術の深化が不可欠です。CC Labは、このような背景を踏まえて、新たに設立され、その使命を果たすために強い意志を持っています。
CC Labの基本情報
CC Labは、以下のような取り組みを行います:
- - ハードウェア型秘密計算に関する研究
- - 学術及び技術コミュニティとの連携
- - 製品開発および評価に関する活動
ハードウェア型秘密計算とは
ハードウェア型秘密計算とは、秘密計算の一種であり、データを暗号化した状態のままで計算を行うことができる技術です。特に、TEE(Trusted Execution Environment)と呼ばれる環境を利用することで、データの機密性を確保しつつ、実行するコードの完全性も保証します。これは、特に政府のクラウド環境などで重要な技術とされています。
さまざまな業界で導入が進んでいるハードウェア型秘密計算は、国内外を問わず注目されています。実際、AppleやGoogleをはじめとした大企業も既にこの技術を採用し、米国の軍隊でも実用化が進んでいます。
Acompanyのビジョン
Acompanyの代表取締役CEOである高橋亮祐氏は、「CC Labの強固な研究開発体制を通して、データとAIの利活用の新たな道を切り開いていきたい」と語っています。CC Labが進める研究が、今後のデータ活用の礎となり、多くの企業や組織に貢献することが期待されています。
名古屋の「CC Lab」の設立は、地域に根ざした技術革新の象徴であり、ますます重要になるデータの安全な利用の実現に向けた一歩となるでしょう。

トピックス(その他)
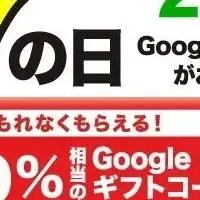
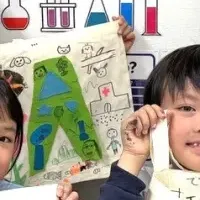

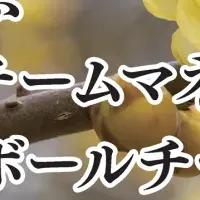
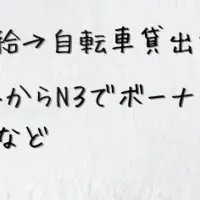


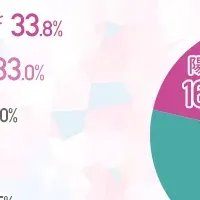
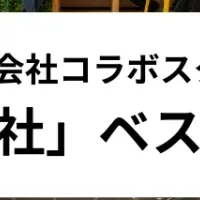

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。