

地域住民と共に未来を築く「ブロッケーション™」の取り組みを紹介
地域住民と未来をつなぐ「ブロッケーション™」
近年、全国各地で頻発する水災害は、人的被害や経済損失を大きく引き起こしています。これを受けて国土交通省は、新たな水災害対策として「流域治水」の重要性を強調しています。そして、その一環として新設された「流域治水オフィシャルサポーター制度」では、 地域の企業や団体が協力し、流域全体を視野に入れた対策を推進することを目指しています。
ブロッケーション™とは?
この取り組みの一環として注目を集めるのが「ブロッケーション™(Block + Education)」という手法です。この手法は、地域住民をはじめ、行政や民間事業者が知識と意識を共有しながら、水災害への対策を考えるための方法です。例えば、愛知県の天竜川下流河輪地区やささしまエリア、岩倉市の五条川を舞台に、地域住民が参加するワークショップを実施しています。
地域連携の意義
「ブロッケーション™」では、産学メディアの連携が鍵を握っています。地域の人々が一堂に会し、相互に意見を交わすことで、共通の認識が生まれ、流域治水が推進されるのです。これは地域の未来を形作る意義深い試みでもあり、参加者同士の交流が新たな視点をもたらします。
特に、子どもたちを対象とした夏休み特別企画では、小学生が参加し、未来の地域づくりについて学ぶ機会が設けられています。このように、世代を超えた交流が地域全体で流域治水の推進を牽引するのです。
流域治水オフィシャルサポーター交流会の概要
令和7年12月3日、東京・新橋で流域治水オフィシャルサポーター交流会が開かれ、同時に「ブロッケーション™」に関するポスター発表も行われます。このイベントでは、各参加企業が流域治水に向けた取り組みを披露し、情報交換を図ることが意図されています。国土交通省が主催し、全国から31事例が集まる予定です。
未来に向けた取り組み
流域治水は単なる防災策にとどまらず、コミュニティ創りや地域活性化とも深く結びついています。参加者は、自分たちの住む地域を守り、未来をより良いものにするために、一丸となって取り組む必要があります。
また、流域治水に対する関心を高めるために、SNSや広報誌を通じて情報発信を行うことも重要です。流域治水オフィシャルサポーターたちは、地域住民が参加しやすく、かつ興味を持てるような工夫を凝らしています。
まとめ
「ブロッケーション™」は、地域住民が主体となって水災害に対抗するための新しい手法です。これを通じて、今後ますます厳しくなる気候変動の影響に備え、地域全体が一つになって未来を見据えたアプローチを進めていくことが期待されています。様々なイベントや交流の場を設け、さらなる協力関係を築くことが、流域治水の実現へとつながります。地域の未来を共に考え、行動していきましょう。



トピックス(その他)



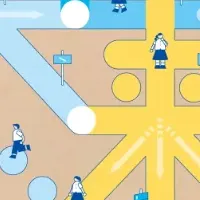

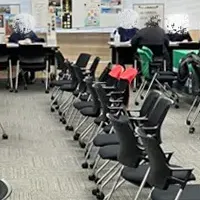

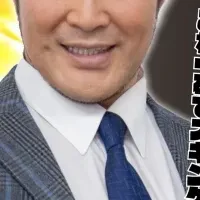
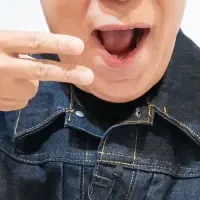

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。