

次世代モビリティを支える東京大学との連携講座の成果発表
次世代モビリティを支える研究成果の報告
株式会社小野測器が、国立大学法人東京大学との共同プロジェクトの一環で、次世代モビリティの研究成果を発表しました。この発表は2025年11月19日、千葉県にある東京大学柏キャンパスで行われ、同社の代表取締役社長・大越祐史氏をはじめ、多くの関係者が参加しました。
研究講座の概要
この取り組みは、「電気自動車の振動計測制御に関する社会連携講座」として、2022年10月に設置されました。目的は「クリーンかつ快適な電気自動車社会の実現」であり、主に電気自動車の駆動モータの高応答性とその制御技術の研究に焦点を当てています。最新技術を駆使し、車両の振動を抑えることで、乗り心地の向上に貢献することを目指しています。
第1期活動の成果
第1期活動では、主に台上試験装置を用いて、新型の平行軸e-Axleを搭載した車両の振動抑制制御を行いました。この研究は、東京大学の藤本博志教授を代表とする研究陣によって実施され、特に実車トランジェントベンチ「RC-S」を利用した試験が行われました。これにより、車両の振動をリアルタイムで測定し、データ分析を通じて制御技術を洗練させることができました。
第2期活動に向けて
2026年から開始される予定の第2期活動では、さらに進化した研究テーマが設定されています。新たに取り組む分野は「自動車用試験装置の制御に関する研究」であり、これにより自動車用試験装置の新たな制御技術を開発することが期待されています。これらの技術は、愛知県豊田市に新設される小野測器の新拠点「中部リンケージコモンズ」に実装される計画です。2027年に稼働するこの新しい施設は、次世代の交通手段に向けた重要な拠点となります。
次世代モビリティへの貢献
小野測器は、自動車だけでなくドローンや空飛ぶクルマ「eVTOL」の開発にも関与することを目指し、次世代モビリティの進展に寄与する研究を行うことを宣言しています。社会的課題の解決にも挑戦し、持続可能な交通手段の実現に向けた活動を展開していくとのことです。
まとめ
このプロジェクトを通じて、小野測器と東京大学は、未来の交通手段の基盤となる技術の開発を進めています。電気自動車の利便性向上や、新しいモビリティの実現に向けた取り組みが、どのように進展していくのか今後の展開が楽しみです。地域社会とのつながりや、未来世代との連携も重視したこの活動は、多くの人々にとっても興味深いものとなるでしょう。



トピックス(その他)





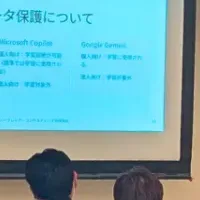
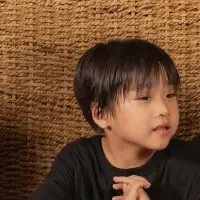
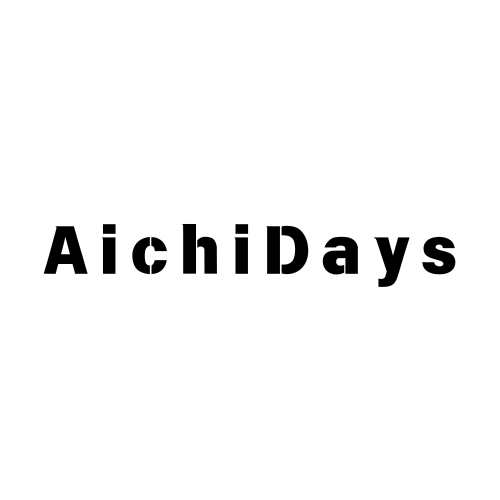

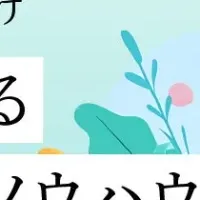
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。