

11月11日は「鮭の日」!サーモン寿司誕生40周年の魅力を探る
11月11日は「鮭の日」!サーモン寿司誕生40周年の魅力を探る
食欲の秋が深まる11月11日、この日は「鮭の日」として知られています。今年はサーモン寿司の誕生から40周年を迎え、回転寿司に欠かせない存在となったサーモンの人気の理由や、養殖技術の進展についてご紹介します。
鮭の日誕生の背景
11月11日とは「ポッキー&プリッツの日」や「おさかなソーセージの日」など、様々な記念日が存在する特別な日です。その中でも「鮭の日」の制定理由は、日本語の「鮭」の構成に由来しています。「鮭」の一部である「圭」は、「11」と「11」の組み合わせから成り立っているため、この日が選ばれたのです。
回転寿司の人気メニュー、サーモン
回転寿司スタイルで現れたサーモンは、日本の食文化に大きな影響を与えています。今年のマルハニチロの調査によれば、サーモンは14年連続でトップの座を維持し、くら寿司の人気ランキングでも2位に位置しているほどの人気です。サーモン寿司は1980年代から広まり、以来日本人の味覚に深く根付いています。生食が可能なこの鮭は、そのアレンジのしやすさも魅力の一つで、サラダやカルパッチョへの活用もすすめられています。
養殖の現状と新しい取り組み
日本は現在、その85%のサーモンを外国から輸入しているものの、国内での養殖も増加中です。特に三陸や九州、さらには淡水での養殖も拡大し、「ご当地サーモン」として各地で特色あるサーモンが育てられています。例えば、青森県の「海峡サーモン」は外海育ちで、強い潮流の中で身が締まった特徴があります。また、兵庫県の「神戸元気サーモン」は酒粕を混ぜたエサで育てられ、栄養価が高いことで知られています。
さらに、愛媛県の「みかんサーモン」では、伊予柑のオイルをエサに混ぜたユニークな取り組みが行われています。フレッシュな風味が際立ち、他に類を見ない特徴を持っています。
ノルウェーサーモンの魅力
ノルウェーからのサーモン輸出は、1980年代から始まりました。当時ノルウェーの水産業者は日本人に向けて、魚の生食文化の高まりを見越して新鮮なサーモンを提供し始めました。今やノルウェーサーモンは世界中で人気を博しており、養殖による安定供給と寄生虫のリスクが低いことで更に評価されています。
特に回転寿司での登場から、家族連れや子供たちに支持されて、ますます受け入れられるようになりました。ノルウェーは、冷たい海で育てられたサーモンを新鮮な状態で届けることを重視しており、現在では日本を含む100以上の国に鮮魚を供給しています。
まとめ
今年の11月11日「鮭の日」を祝うにあたって、サーモン寿司の歴史とその魅力を理解することができました。また、急成長する養殖業とノルウェーサーモンの存在が、日本の食文化に多様性をもたらしていることが判明しました。これからもサーモンが多くの人に愛され続けることでしょう。ぜひ、回転寿司で新しいサーモンを楽しんでみてはいかがでしょうか。










トピックス(グルメ)




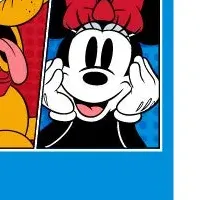
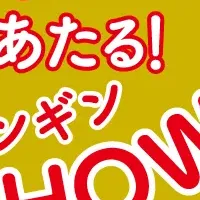




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。