
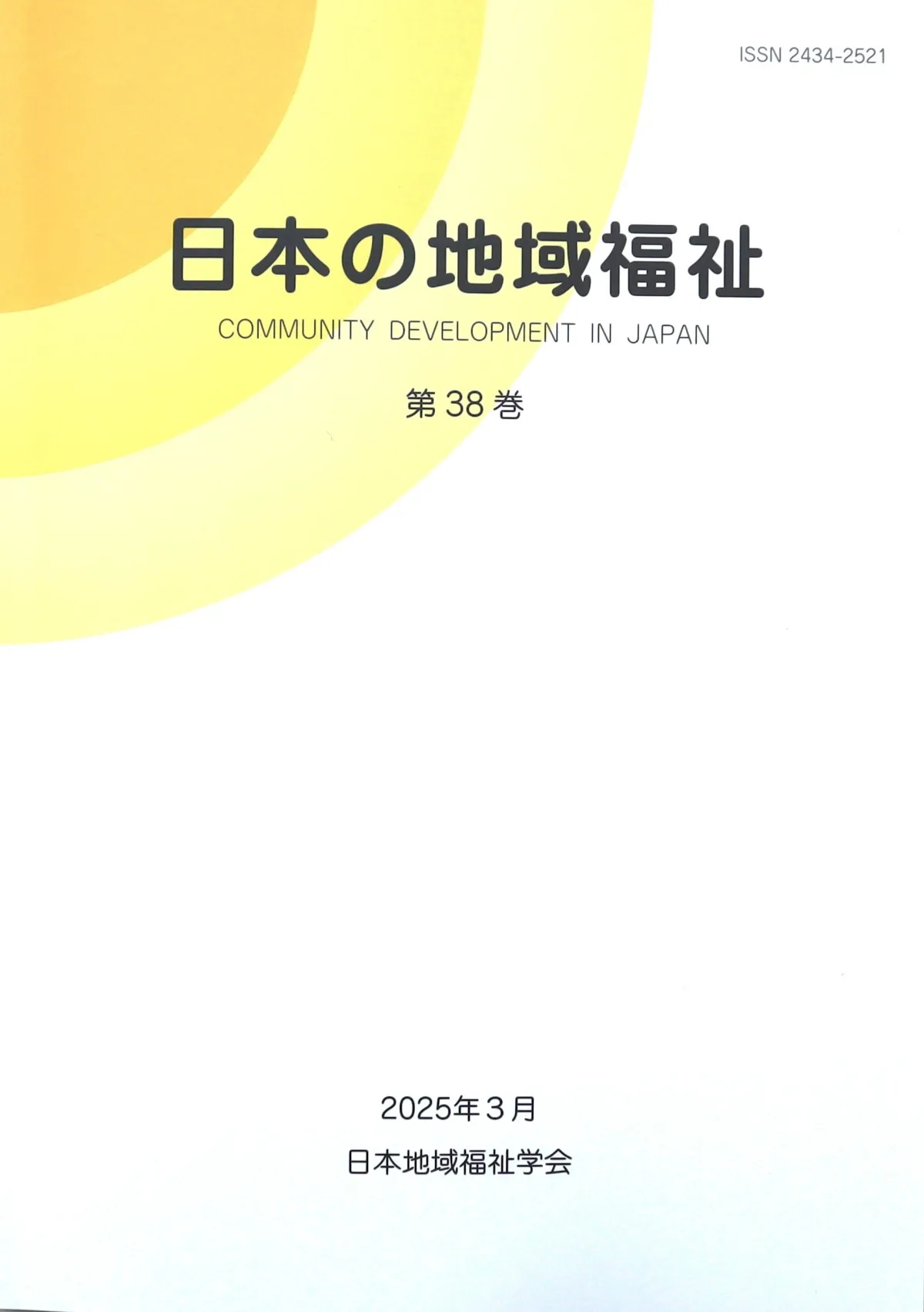
同朋大学の加藤講師が地域福祉の新たな理論を提唱
同朋大学の加藤講師が地域福祉の新たな理論を提唱
同朋大学社会福祉学部の加藤昭宏専任講師が、日本地域福祉学会の機関誌『日本の地域福祉』第38巻に論文を掲載しました。この学会は、実務者と研究者が協働することを重視しており、その特徴が表れています。加藤講師は、日本国内で懸念されている「人材不足・担い手不足」問題に対し、「地域づくり」の推進方法について独自の概念である「関わりしろ」を提唱しました。
「関わりしろ」の概念とは?
「関わりしろ」とは、人と人が関わる際の「のりしろ」とも言えるもので、地域社会での結びつきを強化し、住民同士の交流を促進するための実践スキームを導入する際に用います。これにより、地域の現状に合わせた「結びつき合い」を実現する必要性が示されています。
加藤講師の専門は、コミュニティソーシャルワークの実践理論に加え、包括的な支援体制の構築に向けた方法論です。このアプローチは、地域福祉を進める中で欠かせない要素となっています。
社会福祉学科の学びと役割
同朋大学の社会福祉学科では、少子化や格差問題など、現代日本が直面している様々な社会課題に対し、専門知識と技術を持ち、人々の心に寄り添う「人間力」を育成しています。現場での実習やフィールドワークを通じて、学生たちは実践力を磨き、多様な問題解決に挑む力を身につけています。
特に、社会福祉士を目指す学生にとって、実践的な学びは不可欠です。加藤講師が担当する講義は、学生たちが地域福祉に対する理解を深める上で貴重な機会となっています。これからの福祉の専門家として、彼らは理想的な社会づくりの担い手となることが期待されています。
オープンキャンパスの開催
今年の4月26日(土)には、同朋大学のオープンキャンパスが開催されます。このイベントでは、受験生やその家族に向けて、同大学の特色や魅力を直接紹介します。特に、社会福祉学部の学びを体感できる貴重な機会です。
詳しくは、同朋大学のオープンキャンパスページをチェックしてください。 オープンキャンパス詳細
同朋大学について
名古屋市中村区にある同朋大学では、社会福祉学部や文学部など多様な学科を提供しています。社会福祉学部の中には、心理学専攻・社会福祉専攻・子ども学専攻などが含まれ、各専攻で専門性を深めることができます。クオリティの高い教育を通じて、学生は福祉の現場で求められる知識と能力を身につけることができます。
学長の福田琢を中心に、学生たちが自由に学び成長する環境が整えられています。興味のある方は、ぜひ同朋大学を訪れてみてください。
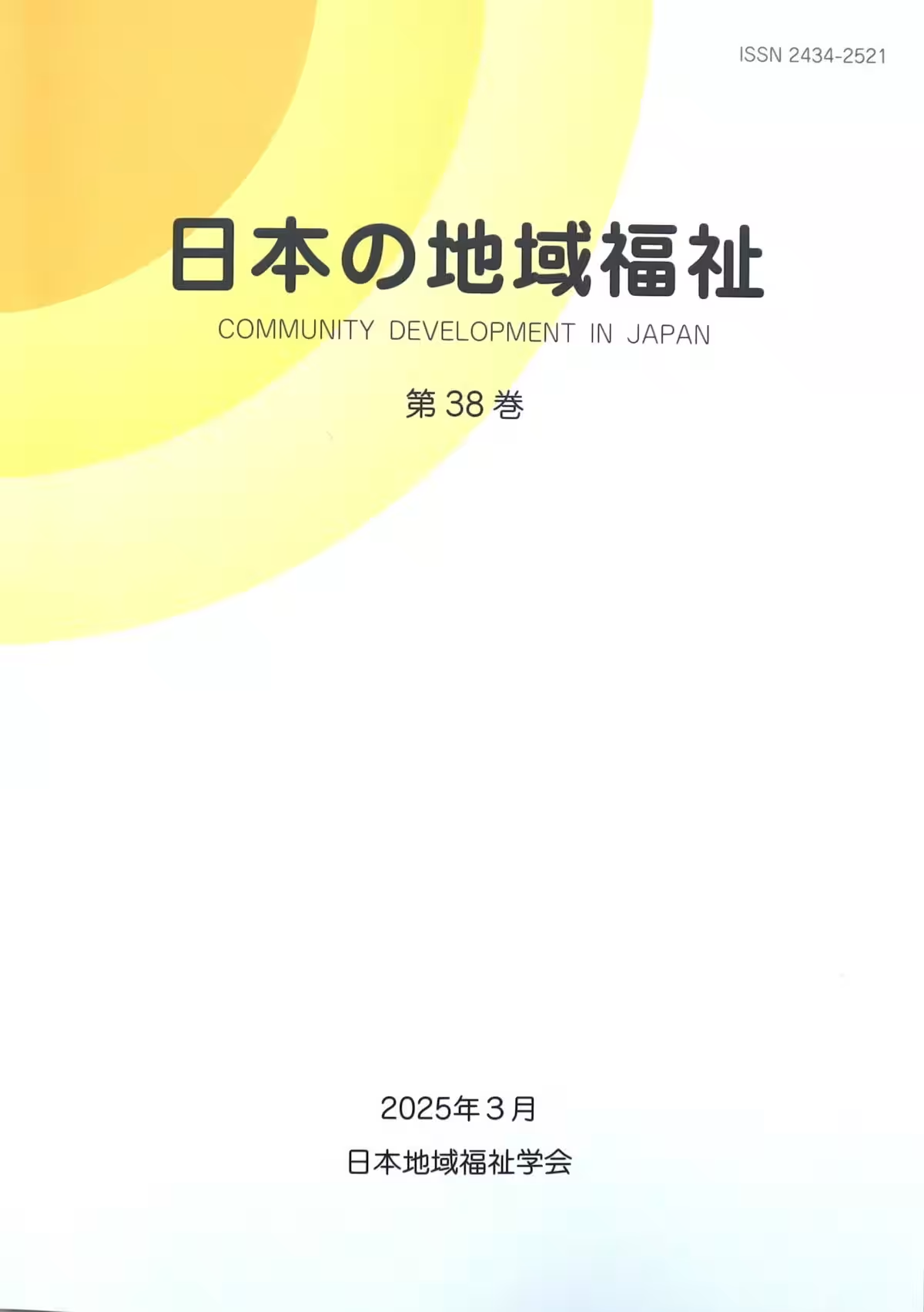


トピックス(その他)


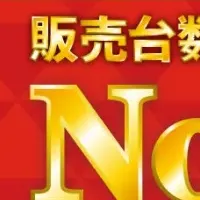

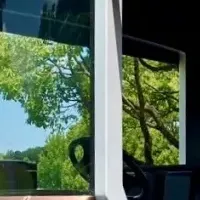



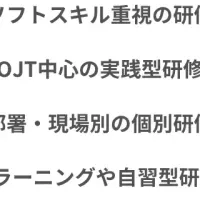

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。