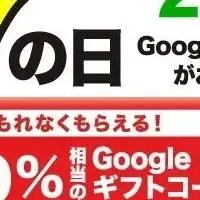

豊田中央研究所が推進する車載用電池の循環型社会実現に向けた取り組み
電池循環型社会の実現に向けた新たな試み
2025年4月23日、豊田中央研究所は車載用リチウムイオン二次電池(LiB)のリユースやリサイクルを介して循環型社会の実現を目指す革新的な研究プロジェクトを発表しました。この「電池循環システム」研究の一環として、新たに提案されたのがLiBのライフサイクル全体における二酸化炭素(CO2)排出を定量的に評価する手法です。
研究プロジェクトの背景
近年、自動車の電動化や再生可能エネルギーの普及が進む中で、リチウムイオン二次電池の需要は急増しています。新たに製造する場合に比べ、リユースやリサイクルを行うことで資源の消費やCO2の排出を削減できる可能性が高いことから、世界各国でリユース/リサイクル技術の開発が進められています。
豊田中央研究所は「電池循環システム」プロジェクトを掲げ、中古LiBを用いた電力のバッファとしてのリユースを促す「SWEEP SYSTEM®」や、使用済みLiBの診断技術「MaMoRiS®」、コバルトフリーの高性能材料など様々な技術の開発に取り組んできました。
新たなLCA手法の提案
今回、同研究所が提案した新たなライフサイクルアセスメント(LCA)手法は、リユースとリサイクルを統合して評価することができる画期的なものであり、従来の手法では個々の工程に特化されがちだった評価を、ライフサイクル全体での環境負荷の観点から行うことを可能にしました。
具体的には、各工程での選択がCO2排出に与える影響を明示することができます。例えば、リサイクルにおける新しい電極材料回収技術のCO2削減効果を定量的に算出することができ、従来の技術との比較が可能です。
持続可能な未来に向けた協力
この新手法は、単に技術開発を行うだけでなく、学術界や研究機関との連携を通じて社会システム全体のデザインにも寄与するものです。専門家たちとの協力を通じて、LiBのリユース・リサイクルに関する将来シナリオの議論が行われ、その重要性が高まっています。これは、サステナブルな循環型社会構築とカーボンニュートラルの実現に向けた重要なステップとなるでしょう。
今後の展望
豊田中央研究所は今後も、リユース・リサイクル技術の革新だけではなく、その効果を最大限に引き出すためのLCAなどの評価手法の発展に努めていく姿勢を見せています。これにより、車載用LiBを巡る循環型社会が実現し、持続可能な資源循環が促進されることが期待されています。
【論文情報】
- - タイトル:Life Cycle Assessment Integrating the Effects of Recycling and Reuse for Battery Circulation
- - 掲載誌:Journal of Power Sources
- - 著者:小林哲郎、近藤広規、佐々木厳(豊田中央研究所)
- - DOI:Journal of Power Sources
本研究の成果をもとに、持続可能な社会の実現に向けた取り組みはますます重要性を増しています。さて、あなたはこの研究についてどう思いますか?ぜひ、感想や意見をお寄せください。







トピックス(その他)
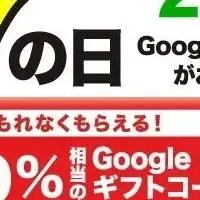
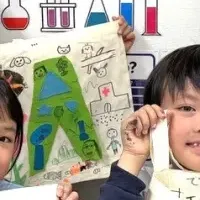

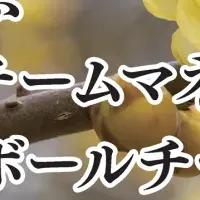
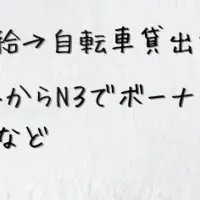


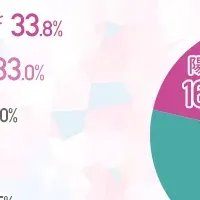
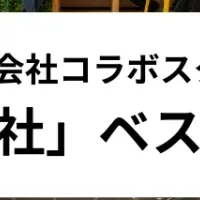

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。